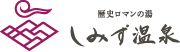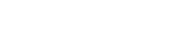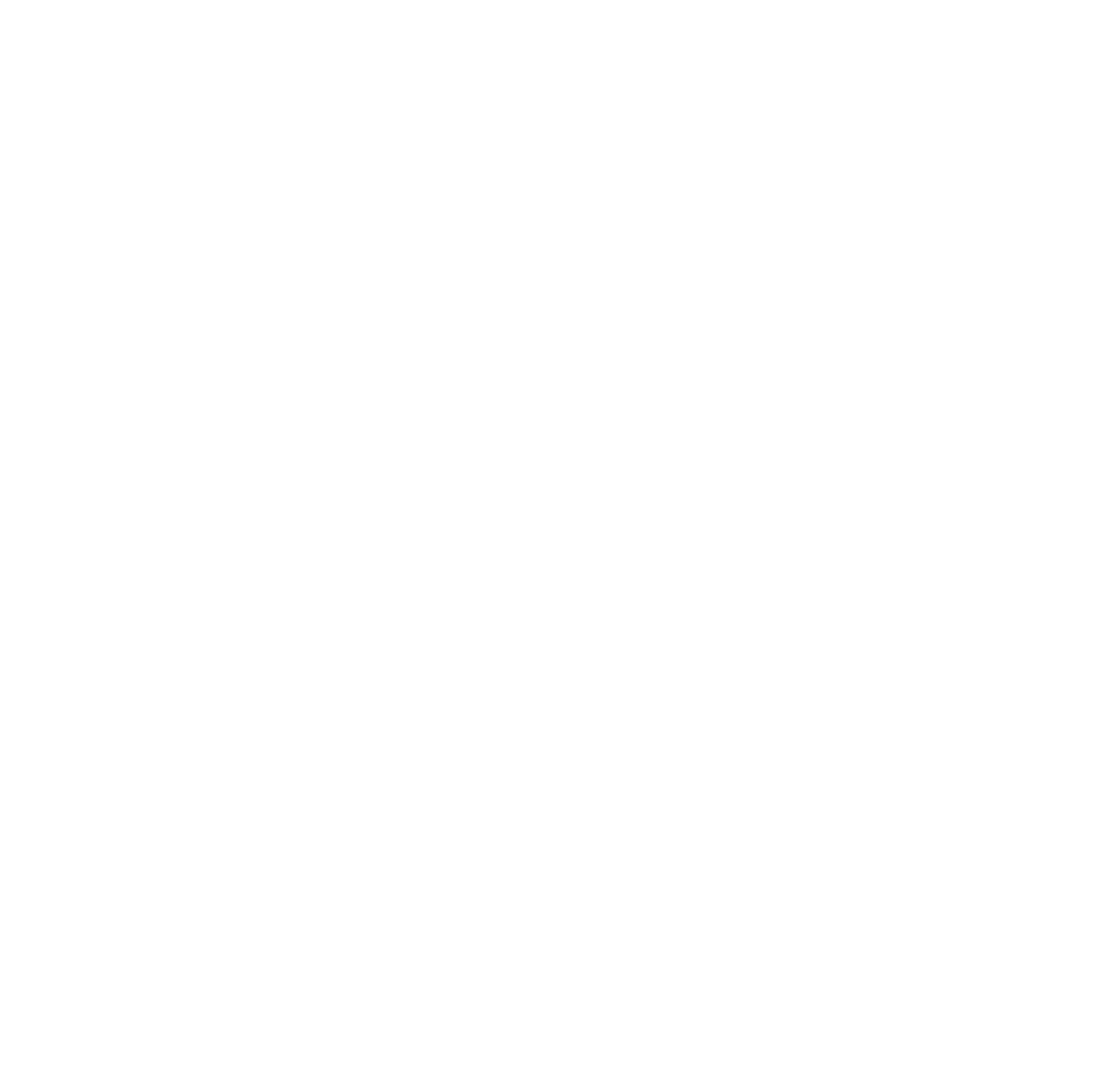あらぎ島
有田川が大きくカーブしたところに、50枚あまりの田んぼが切り立った土手にある。これが、和歌山県中部の山間地で農民たちに貴重な耕地を提供しているあらぎ島の棚田だ。その文化的意義と自然の美しさが認められ、政府は2013年、あらぎ島の棚田とその周辺地域を重要文化的景観に指定した。
文化的景観とは、人と自然が協力して発展してきた地域のことで、特定の環境の中で人々の生活や生業がどのように発展してきたかを示す貴重な例である。指定されると文化財保護法に基づく保護と、保存、研究、教育のための財政的支援を受けられる。
生命の水を育む源
この地は、米が主食であっただけでなく、税金を納めるための通貨でもあった1655年に作られた。笠松佐太夫(1598-1673)という先見の明のある庄屋が、米の生産が村の繁栄につながると考え、地域を豊かにするために水田を開墾した。
開墾努力のひとつとして、佐太夫は私財を投じて、全長3.2キロの用水路を建設した。この用水路の建設は技術的に難しく、労力もかかったが、あらぎ島やその他の低地での米作のための新鮮な水が得られるようになった。当初の用水路は粘土で作られていたため、頻繁に管理と補強が必要だった。1953年の大洪水の後にコンクリートで補強され、用水路は現在も使用されている。
運河から供給される新鮮な水のおかげで、手漉き和紙産業も発展し、この地域はさらに豊かになった。保田紙として知られる、厚くて丈夫な紙は、楮(こうぞ)の繊維から作られる。あらぎ島では、農家が田んぼと田んぼの間の土手で楮を栽培するようになった。保田紙は主に傘や扇子の材料として使われていたが、現在ではカードや封筒などさまざまな製品にも使われている。
自然との調和
あらぎ島の棚田は、かつて山村では一般的だった水辺の植物や動物にとって重要な生息地となっている。和歌山では絶滅危惧種に指定されているアカハライモリなどである。単なる水草から、食物連鎖を通じて猛禽類に至るまで、有田川町の田んぼは生命に満ち溢れ、地域の人口をはるかに上回る生命を維持している。過疎化や農村再編により山間部の水田が減少する中、その重要性はますます高まっている。