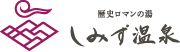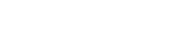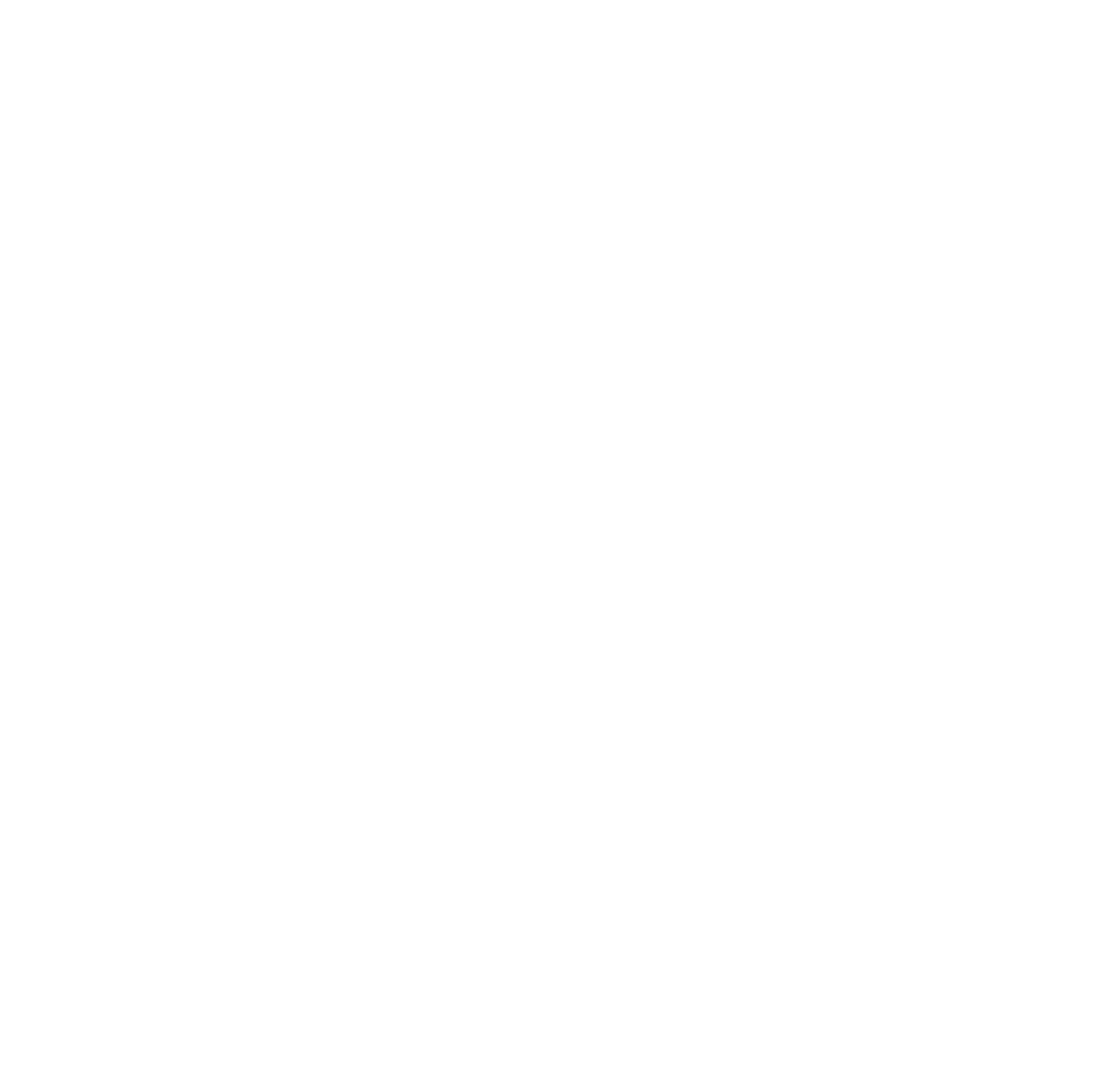地域社会における神社・仏寺
日本を訪れる観光客の多くは、都会的で大きな寺社仏閣を思い浮かべるだろう。京都の金閣寺の豪華絢爛な黄金の塔や、東京の浅草寺の賑やかな参道などだ。有田川町のような人里離れた山間部の寺や神社は、それほど広大でも壮大でもないが、それでも日常生活や習慣の中で重要な役割を果たしている。
有田川町の寺や神社は通常、神を祀る小さな建造物1つで構成されている。扉は通常、神への敬意から閉ざされたままだが、祭事の際には開けられることもある。通常、人は常駐していない。その代わり、地元の住民が境内や建物の管理・維持に当たっており、中には少なくとも500年以上使われているものもある。
日本の多くの宗教施設は、自然の美しさを誇る場所でもある。有田川町の寺社の多くも木陰や山頂にひっそりと佇む。その入り口は無名の目立たない場所にありがちだが、それらを探し求める観光客は、文化と自然が融合したユニークな風景を目にすることができるだろう。
このような孤独になりがちな場所は、年に一度のお祭りのときに最も賑やかになる。有田川町の多くの寺社では、縁起を担いで餅まきが行われる。小さな餅が壇上から下に集まった人々に投げられ、人々は縁起の良い餅を取ろうと競い合う。