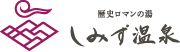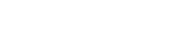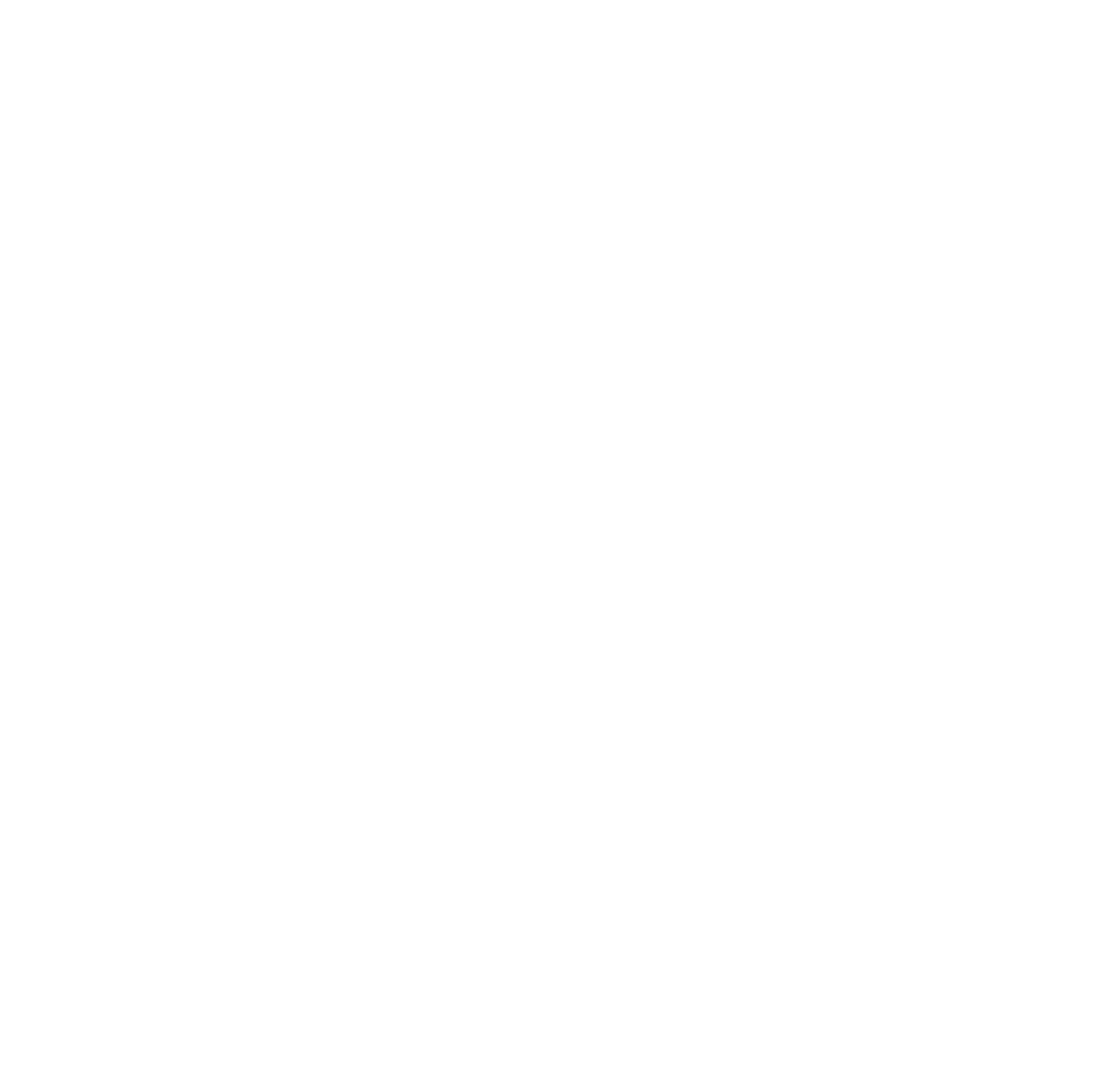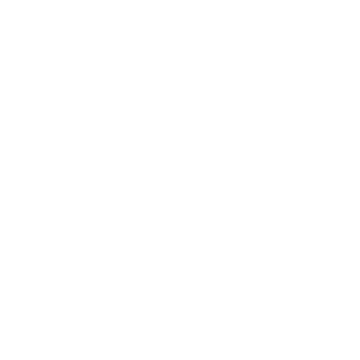上湯用水路
上湯用水路は、現在の有田川町に水を供給するために1600年半ばに建設された。全長3.2キロの用水路は、風光明媚なあらぎ島の棚田のような新しい水田や製紙業が発展を可能にした。
この事業は、笠松佐太夫(1598-1673)という先見の明のある庄屋資金提供したもので、彼は地元の米の収穫量を増やすことで貧困を緩和しようとした。近代的な測量器具も掘削機械もない山間部を切り開かなければならなかったため、労力は相当なものだった。現存する記録によると、水路は1655年に完成した。
元々、この水路は土で作られたもので毎年春になると、頻繁に弱い部分がないかを点検し、補強しなければならなかった。地元住民は約300年間、この重要なインフラを集団で管理した。1953年の壊滅的な洪水の後、土はより弾力性のあるコンクリートに取り替えられた。
上湯用水路は現在も使用されており、元のコースに沿って約13.5ヘクタールの農地に灌漑用水を供給している。この用水路は、有田川町の歴史と文化の中で重要な役割を果たしていることが評価され、2013年に選定された重要文化的景観「蘭島及び三田・清水の農山村景観」に含まれている。