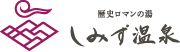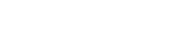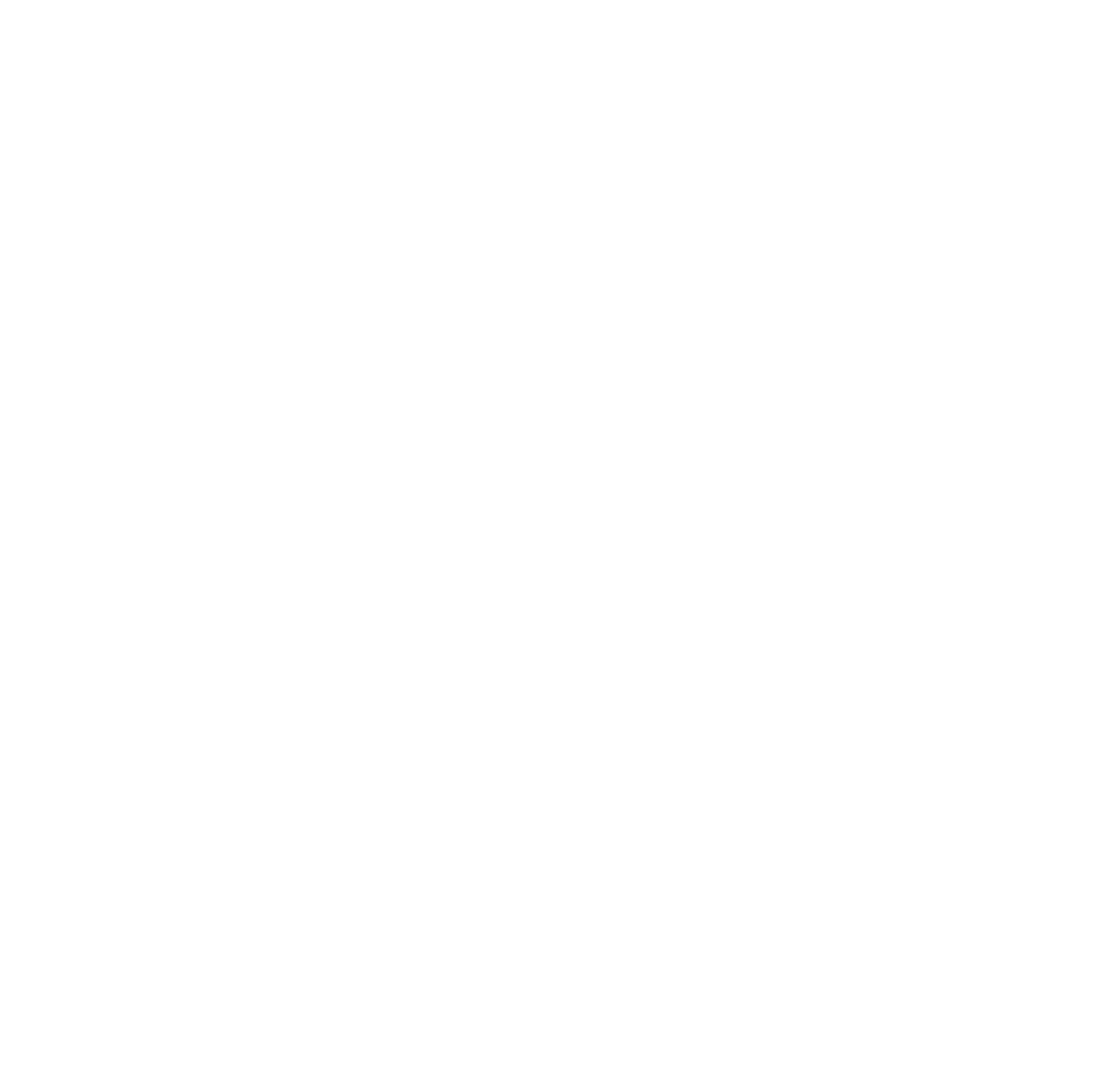保田紙
保田紙は、白くて破れにくいのが特徴の手漉き和紙の一種である。約360年前から歴史ある有田川の清水地区で生産されてきた。旧紀州藩(現在の和歌山県)にちなんで紀州手漉き和紙と呼ばれることもある。
保田紙の歴史
近世の日本では、米、塩、紙の3つが最も重宝されていた。1619年に徳川頼宣(1602-1671)が紀州藩主になったとき、彼の領地には米と塩はあったが、紙が生産されていないことを知った。これを改善するため、頼宣は庄屋であった笠松佐太夫(1598-1673)に命じて有田川町に紙漉き場を作らせた。佐太夫は他藩の紙漉き場を訪ねて技術を学ぼうとしたが、職人たちが自らの企業秘密を守ろうとしたため、門前払いを食らった。そこで佐太夫は一計を案じ、3人の美男子を現在の奈良にある吉野の紙漉き地区に移住させた。彼らは徐々に地域に受け入れられ、やがて地元の紙漉き職人の女性と結婚した。そして男たちは、自分たちの製紙業を確立するための知識を携えて、花嫁とともに有田川町に戻った。最盛期には、傘や扇子、書類などの紙を作る家が400軒もあったという。
保田紙の製法
保田紙の製造は、熟練した技術と経験を必要とする、時間と手間のかかる工程である。現在でも、ほとんどの作業は手作業で行われている。主な原料は、1月に収穫される楮(こうぞ)の樹皮である。樹皮は剥ぎ取られ、洗浄され、冬の風にさらされ、煮沸され、きれいに取り除かれた後、水で叩かれて柔らかくなり、繊維が分離される。その後、繊維をネリ(トロロアオイの根から抽出した粘性のある物質)と一緒に水に入れられる。湿度や気温に合わせて異なる量の糊が使用されるが、その比率は完全に経験と感覚によって決定される。木枠に張った和紙をスラリーの中にくぐらせ、パルプが均一に広がるまで揺する。その後、余分な水分を除去するためにプレスし、丹念に木製の乾燥板にブラシで刷り込む。ブラッシングが強すぎると紙が破れてしまうし、ブラシが不十分だと紙が板にしっかりと接着せず、天日干ししたときに縮んでしまう。
保田紙の現在
保田紙は、大量生産紙との競争、洋傘の流行の普及により、和紙の市場は激減し、保田紙の生産はほぼ消滅した。1953年の大洪水により、残っていた紙漉き場の多くが壊滅的な被害を受けた。1979年、残された紙漉き職人たちは、その技術を伝承し、和紙工芸への関心を促進するための機関を設立した。その構想は、「体験交流工房わらし」の運営に繋がり、現在では、一般客が和紙漉きを体験できる本格的な紙工房となっている。